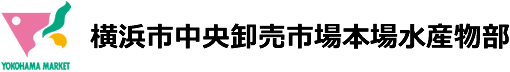魚市場ブログ
漁業権と市場法の改正がもたらす本当の危機
こんにちは。
今回はちょっと真面目な話です。
私たちの食卓に当たり前のように並ぶ「魚」。
その魚が、今後食べられなくなるかもしれない——そんな現実が、静かに進行しています。

🐟 サーモンはもう外資の支配下?
近年、ノルウェーやアラブ資本などの外国企業が、日本国内でサーモン養殖を始めています。
-
🇳🇴 ノルウェー:静岡県で完全陸上養殖(Proximar Seafood)
-
🇦🇪 アラブ首長国連邦:三重県で養殖計画中(Pure Salmon)
どちらも高級志向のアトランティックサーモンを養殖し、輸出も視野に入れています。
つまり今後、「外資が育てた魚を日本人が買う」時代が当たり前になる可能性があるということです。
⚠️ 法改正で、なぜこんなことが可能に?
背景には、2020年施行の「改正漁業法」があります。
-
従来は、地元の漁協や漁師に優先的に与えられていた漁業権の優先ルールを廃止。
-
外資を含む企業も、条件を満たせば養殖に参入可能に。
これは「成長産業としての水産業育成」を目的とした政策でしたが、結果として日本の漁業が企業の利益優先にシフトするリスクをはらんでいます。
📉 なぜ政府はこんな危険な制度を通したのか?
いくつか理由があります。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 成長戦略 | 水産業を民間・外資の力で効率化したい |
| 漁師不足 | 「地元が使えてない漁場を企業に任せたい」 |
| 国際圧力 | WTOや貿易協定からの開放要求への対応 |
| 官僚の論理 | 改革=実績。現場よりも制度変更を優先 |
ですが、こうした「上の理屈」によって、地元漁師や日本人の食卓が危機にさらされているのです。
🧂 市場法も同じく「ヤバい」
2020年には卸売市場法(市場法)も改正され、公設市場の義務がなくなり、
誰でも市場を開設できるようになりました。
結果として、
-
中央卸売市場の価格の透明性や公共性が後退
-
流通のプロよりも、民間の利益優先が目立つように
本来、市場は「国民に安定して食を届けるための公的なインフラ」だったはずです。
🔚 このままでは、魚は輸出用になる
-
外資の養殖魚は、高値で売れる海外に優先的に流される可能性があります。
-
日本国内には、価格の上がった魚しか残らない。
-
中小の漁師は撤退し、私たちが手ごろな価格で魚を食べる時代が終わるかもしれません。
最後にこの問題は「漁師の話」ではなく「私たち全員の話」
魚は、単なる商品ではありません。
文化であり、暮らしであり、命をつなぐ食の柱です。
それが、静かに、確実に、利益の論理で壊されようとしています。
「気づいたときにはもう遅かった」では済まされない問題です。
今こそ、現場の声と生活者の視点で、水産と食のあり方を見直すべき時ではないでしょうか。